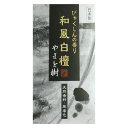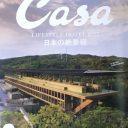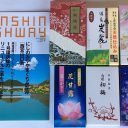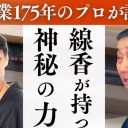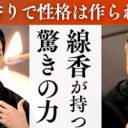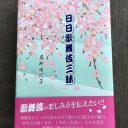香木・香料のはなし -丁子-

丁子
香木・香料のはなしの第三回目のテーマは「丁子」です。
丁子(ちょうじ)は、フトモモ科の木であるチョウジノキの開花前の蕾を乾燥させたものです。その形状が釘に似ていることから丁子という名が付けられました。原産地はインドネシアのモルッカ諸島といわれています。現在では、インドネシアや東アフリカが主要な生産地となっています。
料理をされる方とっては、丁子というよりもクローブと言ったほうが馴染みがあるかもしれません。肉料理やカレー、スープ、ソースなどの香辛料(スパイス)としてよく用いられています。強い甘い香りと舌にピリッとするような刺激味が特徴です。

丁子
※画像は(株)長川仁三郎商店からご提供いただきました。
丁子は紀元前よりインドや中国で殺菌・消毒剤として使われていました。口臭消しや歯痛を和らげたいときに噛むなどされていたことが記録にも残っています。また、ヨーロッパでも14~16世紀の大航海時代には、コショウなどと並び香辛料貿易の中心商品であり、生産地の覇権をめぐって様々な国が争奪戦を繰り広げました。
日本でも丁子は古くから親しまれ、正倉院の御物の中にも見られます。平安時代に書かれた「源氏物語」の中には「丁子染」という記述があり、これは丁子を染料として絹を染めあげたものです。(香料を使って染めたことから、「香染」と記されていたりもします。)また、密教では、今なお含香(がんこう)として勤行前などに丁子を刻んだものを口に含み噛んで口内をお清めるのに使われています。さらに江戸時代には、香料として丁子を利用した鬢(びん)付け油の「伽羅の油」が庶民の間で大ヒットしました。(ちなみに、伽羅の油には本物の伽羅が使われていた訳ではありません。)
その他、丁子は香料としてだけでなく、薬、防虫剤、刀の錆止めなど様々な用途で使われてきました。丁子は、日本人の生活において、今も昔も変わらず非常に馴染み深いものです。