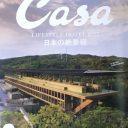誰が袖のはなし

誰が袖(たがそで)
「色よりも香こそあはれと思ほゆれ 誰が袖ふれし宿の梅ぞも」(古今和歌集・詠人知らず)という和歌があります。現代風に訳すと「梅はその色彩よりも香りの方がしみじみと趣深く思われる。宿の梅に誰かの袖がふれて、その移り香が香っているのだろうか。」といったところでしょうか?「梅の良い香りがするので、どのような高貴な人の移り香かと想像している…」、そんな光景が思い浮かびます。
さて、衣服の袖の形に作った袋を二つひもで結び、香料を刻んで調合したものを詰めて携行できるようにした「匂い袋」のことを「誰が袖(たがそで)」といいます。着物の両方の袂(たもと・和服の袖付けから下の袋のように垂れた部分)の中に「誰が袖」を入れてその香りを楽しみます。
この「誰が袖」は室町時代後期に流行したのですが、そうした背景には、武家という新たな支配階級の登場によって、お香の楽しみ方にも変化が生じたことがあります。我が国では平安時代、公家貴族を中心に、室内で用いる薫物(たきもの)が発展しましたが、鎌倉時代、室町時代には武士が主導権を握る時代になると、香りも外に持ち歩きのできるものへと変わっていったのです。(武家の誕生とお香の楽しみ方の変化については、「家康とお香のはなし」の中でも触れていますので是非ご参照ください。)
「誰が袖」という呼び名は冒頭の和歌に由来するものですが、「匂い袋」のことを「誰が袖」と呼ぶあたり、日本人らしい美意識が感じられます。